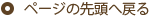目次
 第三章
第三章
神武東征
神武東征
(1)日向から岡田宮
神武東征譚はあまりにも有名であり、ここでは、まず『記』に従って略記する。
磐余彦(後の神武天皇、以後、神武と記す)は、兄の五瀬ともに、日向の高千穂で、葦原中国を治めるにはどこへ行くのが適当か相談し、東へ行くことにした。舟軍を率いて日向を出発して筑紫へ向かい、豊国の宇沙(宇佐市)に着く。そこでは宇沙都比古と宇沙都姫の二人が仮宮を作って食事を供した。そこから移動して、岡田宮に至り一年を過ごした。 神武の舟軍の出発地は『記紀』に記載は無いが、日向市の耳川の耳津(美々津)との伝承がある(図1)。

碑にそえられた神武の軍船
台与は、京都郡に遷都した「台与の邪馬台国」で死去し、後に宇佐神宮が山麓に建つ御許山山頂の三つの巨石(磐座)のうちの中央の岩を依代として葬られていた。後世、宇佐神宮が帰化秦氏により建立された時、その中央の二之御殿に比売大神として祀られたと、私は判断している。残った有力豪族は、後世、景行天皇の討伐に遭うことになるが、景行天皇紀では逆賊として名前も住居も貶められて著されている。詳細は景行天皇章で記す。
次に遠賀潟の岡田宮に向かっている。わざわざ潮の流れの激しい関門海峡を渡ってである。おそらく洞海湾を通って、遠賀潟に入ったのであろう。神武のこの旅程は謎と言われているが、私は次の目的のためと考える。その一つは、五瀬が奴国に戻った母の豊玉姫に会うため。そして磐余彦は、母の玉依姫を生まれ故郷に送るためである。奴国に戻った豊玉姫には、その後の伝承は無い。しかし玉依姫には、伝承が残っている。奴国の志賀島を臨む陸側の宗像市田野字依岳(湯川山)に依岳神社があり、主祭神は依岳大神であるが、『筑前國續風土記拾遺』の依嶽神社の項には、「社家の説に玉依姫命を依岳明神といふ。玉依姫命日向高千穂の嶽より是國に移らせ給ひ、先づ竈門山に住、又此依嶽に移らせ給ひしと云、當郡六箇嶽の一にして所謂筑前の木綿間山是也 (今よこなまりて湯川山と云ふ)」とある(正見行脚 Web)。中継地の宝満宮竃門(かまど)神社の上宮は玉依姫を主祭神としているのだ(天武天皇二年の創建)。上宮のある宝満山からは博多湾に浮かぶ能古、志賀などの島々が望め、玄海の波濤遥かに壱岐島を遠望出来る(図2)。

博多湾に浮かぶ能古、志賀などの島々

二つ目は遠賀潟流域で大型舟を建造させるため。日向では、技術や道具の不備で多数の軍衆を乗せる大型の船の建造が出来なかったと思われる。三つ目は、日向の狗奴国からの友軍と奴国からの援軍を迎え入れるためである。東征で活躍する久米の兵士は、黥利目 (さけるとめ、入墨をした目) をしており、阿曇目をしている安曇氏と同じであり、奴国の安曇氏の一部族であったのであろう。舟団と兵士を整えた神武軍は、遠賀潟から洞海湾を抜け、関門海峡を通って、瀬戸内海に至ったと、私は考える。『記紀』の記述とは異なる私見であるが、関門海峡を出たところの速吸門(はやすいのと)で、国神の珍彦(うずひこ、槁根津彦)に出会ったとしたい。珍彦は瀬戸内海の海路に詳しかったようで、神武の舟軍を河内の国の草香邑まで案内できたのだ。私は、珍彦は吉備の者としたい。その理由は後に記す。