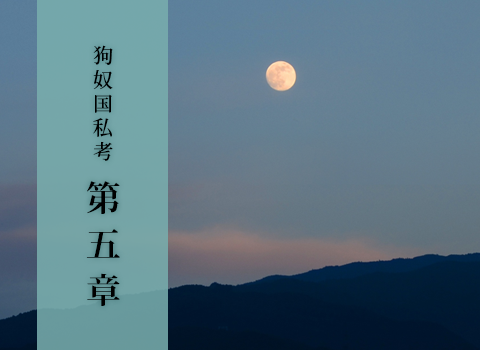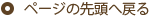目次
 第五章
第五章
崇神天皇と神々の祟り
十代崇神天皇
(12)三角縁神獣鏡の始まり
『記紀』ともに崇神天皇が三角縁神獣鏡を作る詔を出したとは書いていない。神社奉納用の矛や太刀は作らせているが。したがって、三角縁神獣鏡の鋳造は崇神王権が関与しない事柄であったとすべきである。しかし、崇神天皇は確かに鏡を作らせている。唐子・鍵(磯城郡田原本町)付近の鏡作にある「鏡作坐天照御魂神社」の由緒には、「崇神天皇六年九月三日、この地において日御像の鏡を鋳造し、天照大神の御魂となす。 今の内侍所の神鏡是なり。本社は其の(試鋳せられた)像鏡を天照国照彦火明命として祀れるもので、この地を号して鏡作と言ふ。」とある(図4)。


「三神二獣」三角縁神獣鏡の内区
大陸では280年に西晋王朝が呉を滅ぼして華北と華南を統一していた。この頃、華北ではよい鏡は流行していなかった(獣首鏡、盤龍鏡、夔鳳鏡、位至三公鏡など)。反面、呉が支配していた華南では、画文帯神獣鏡や画像鏡など文様の精緻な鏡が流行していた。これらの鏡の文様は神(東王公、西王母、黄帝、王喬など)や瑞獣(青龍、白虎、獅子、辟邪)などを鋳だし、また、神や瑞獣は半肉彫りで表わされており、倭人にも理解できやすかった。神を鋳だした鏡は、崇神天皇の神を崇める風潮にも合致した。宇摩志麻治は台与が築いた西晋王朝との冊封体制を利用して、呉地域で流行していた鏡を輸入した。崇神天皇の陪冢天神山古墳の画文帯神獣鏡や画像鏡、奈良県桜井市ホケノ山古墳の画文帯同向式神獣鏡はその例といえよう。画文帯神獣鏡の画文帯の文様は複雑精緻で、倭人の鋳造師集団には理解も模倣できなかった。そこで、彼らは、画文帯神獣鏡の内区の神や瑞獣および画像鏡内区の神や瑞獣を採用し、外区は画像鏡の鋸歯文と二重波線文を採用したデザインの鏡を創作した。外縁を断面が三角形になるように設計したため、現在では三角縁神獣鏡と呼ばれている。しかし、倭人は画像鏡にある羽人(手足に羽を持ち空を飛回る事ができる仙人)は全く理解できず、結果として笠松文としてあらわされた。車馬もなじみが無く、当初は模倣したが次第に使われなくなった。また、漢字は理解できなかったが「天王日月」は正中線にそって左右対称であり、鏡字になっても「天王日月」と表わされることから、デザインとして採用された。以上のデザインになる鏡として、愛知県東之宮古墳出土の唐草文帯三神二獣鏡、乳唐草文帯三神二獣鏡として兵庫県ヘボソ塚古墳三神二獣鏡、大阪府紫金山古墳の唐草文帯三神二獣鏡、唐草文帯三神三獣鏡および獣紋帯三神三獣鏡、岡山県車塚古墳複波文帯六神四獣鏡、香川県茶臼山古墳乳獣紋帯三神三獣鏡、岡山県円山古墳唐草文帯二神二獣鏡、滋賀県大岩山古墳三角縁竜虎鏡などがあげられる。中でも、崇神天皇の陪冢である天神山古墳に埋納されていた「西王母東王公竜虎画像鏡」(奈良国立博物館、727ー11)をモデルにして黒塚古墳8号鏡「三角縁神人竜虎画像鏡」が作られた事は間違いないであろう。