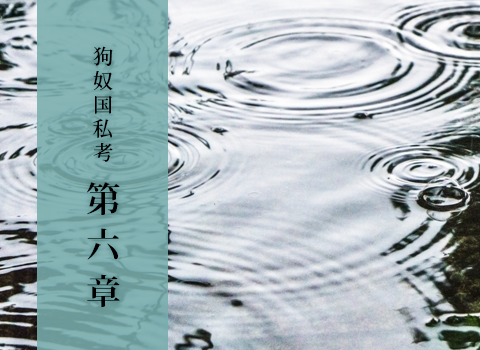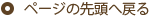目次
 第六章
第六章
狗奴国王統の盛衰
十三代成務天皇
(1)政務をこなした天皇
成務天皇の実質の事蹟は成務五年までである。なぜ、これほど短いのか? これほど短い事蹟年数しか持たない天皇をなぜ創作しなければならなかったのか? それについて考えてみよう。『記紀』の解説では成務天皇の実在を否定する。私はそうは思わない。垂仁天皇は二人の御子の五十瓊敷入彦(いにしきいりびこ)と大足彦に皇位継承を尋ねた時、兄の五十瓊敷入彦は弓矢が欲しいと言い、弟の大足彦は皇位と答えたので、大足彦が景行天皇になった。その五十瓊敷入彦は垂仁紀では、軍事と政務に専念してきた。例えば、
垂仁三十五年、五十瓊敷入彦命は河内国の高石池、茅渟池を作る。また、倭狭城池、迹見池を作る。さらに諸国に令して、多くの池や溝を開かせた。農業が盛んになり、百姓が富み豊かになった。
垂仁三十九年、茅渟菟砥川上宮で一千口の大刀を作り、石上神宮の神宝に納めた。
垂仁八十七年、五十瓊敷入彦命は年老いたとして、石上神宮の神宝の管理権を妹の大中姫に譲ろうとするが断られる。結局、物部十千根大連が管理することになる。
外征に飛回った武勇の倭建の陰に隠れ、大和で王権の政務を取り仕切った五十瓊敷入彦を成務天皇として仕立て上げ、その功績を讃えたと、私は判断する。景行天皇紀で、成務天皇になる稚足彦(わかたらしひこ)は、倭建や五邇百城入彦とともに大和に残り、地方に下向していない。五十瓊敷入彦が稚足彦のモデルになっているのだ。
治世元年(辛未年)、
物部胆咋宿禰を大臣として志賀高穴穂宮に都を置いた。
成務三年、武内宿禰(たけしうちのすくね)を大臣にして政務を統括させた。
成務五年、山河で国・県の境を定め、国造、郡長、県邑の稲置(首長)を定め、地方支配の基礎を固めた。それにより民百姓も安心して居住が出来るようになり、天下が安定した。
まさに、政務に専念したのである。ただし、成務天皇(つまり五十瓊敷入彦)の没年の干支は、景行天皇から一回り後の辛未となっているが、事蹟のある五年は加味して、崩御年の西暦は380年頃としてもよいのではないだろうか。
天皇の陵墓の比定は難しいが、現在比定されている成務天皇陵(佐紀石塚山古墳)の脇には垂仁天皇の皇后、日葉酢媛(ひばすひめ)の狭木之寺間陵(佐紀陵山古墳)が寄り添う様にある(図6)。