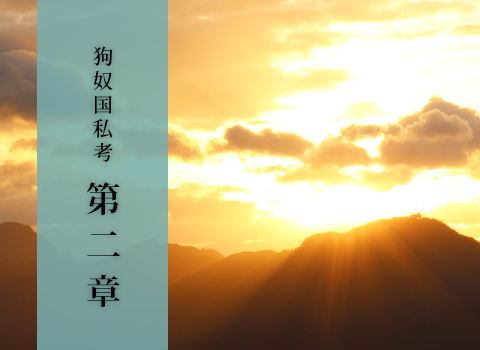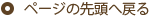目次
 第二章
第二章
邪馬台国の卑弥呼と天照大神
宇佐神宮の比売大神の正体
私が考える不弥国比定域に製鉄所の遺跡はないようである(近代では、北九州市は製鉄都市であるが・・)。それでは、鉄はどのようにして入手したのであろうか? 『魏志』東夷伝弁辰条は記す「國出鐵 韓濊倭皆從取之」(国には鉄が出る。韓人、濊人、倭人はこれをほしいままに取る)。これは、邪馬台国の時代、倭人が弁辰(加羅の領域?あるいは弁韓と辰韓)に住み、鉄鉱石を採って、製鉄をしていたことを示す。勿論出来上がった鉄を倭国に移入するためである。倭国は、韓人がつくった鉄を全面的に輸入していた訳ではないのだ。倭国内で必要な鉄を半島南部の弁辰に製鉄に行っていたのである。不弥国の物部氏族に鉄を供給したのは隣の宗像の海人であったのであろう。そして物部氏族を介して「台与の邪馬台国」は宗像氏とも交流を深め、宗像氏は鉄の移入だけでなく、饒速日の魏や西晋王朝への朝貢に積極的に働いたのであろう。狗奴国の本貫国である奴国の頭領の安曇氏の海人は、用いる事は出来なかったからである。
豊前に遷都してきていた台与は、死後、遥か東方の河内・大和から偲ぶことが出来る国東半島付け根に立つ御許山(図11)の山頂の三つの岩(磐座)のうちの中央の巨磐を依代に葬られたとしたい。


「台与の邪馬台国」の東遷時代は、狗奴国出身の邇邇藝から神武までの三世代が日向灘に臨む延岡平野から宮崎平野にかけて暮らしていたほぼ50年間にあたる。神武は軍舟団をしたてて東征し、本州島で邪馬台国(連合)の後裔と激しく抗争した後に大和に王権を樹立する。その後も狗奴国後裔と邪馬台国(連合)後裔は王権をめぐり抗争を繰り広げるのである。この論考については今後述べていきたい。
*大國主の国譲り後、葦原中国(本州島と四国島)に東遷した邪馬台国連合の権力者や卑弥呼の後裔の活躍は、『記紀』にほとんど記されていない。この時代については、考古資料をもって解明するしかない。では、なぜ無いのか? 東遷した邪馬台国連合の権力者や卑弥呼の後裔の支配地域があまりも広大で、猿女君が十分にカバーできなかったとも言えるが、邪馬台国の後裔の活躍が『記紀』編纂時に抹消されたともいえよう。抹殺したのは誰であるのか? 私は天武天皇としたい。理由は天武天皇紀で詳述する。
美典 国立天文台報 第14巻 2012年
史~風土記逸文 露草色の郷 Web